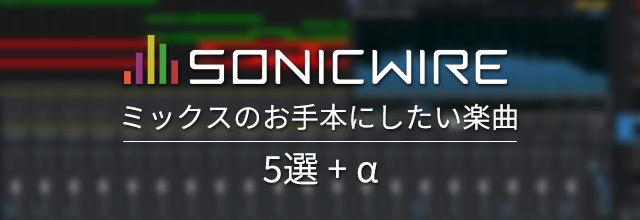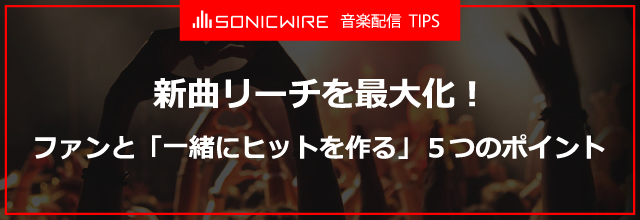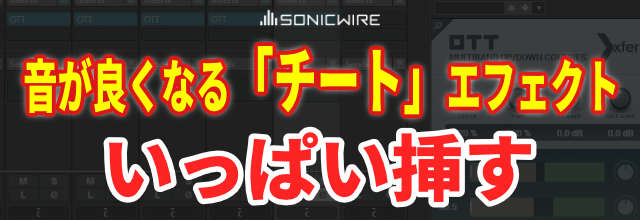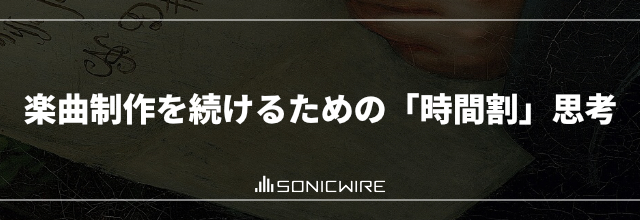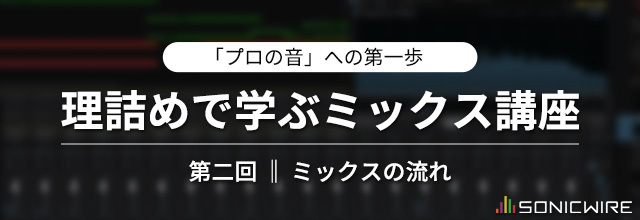
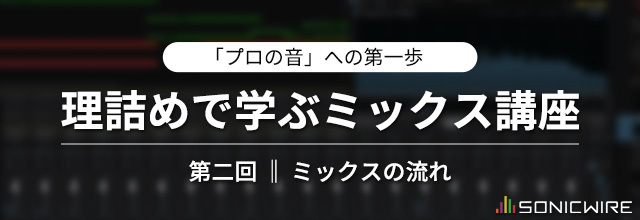
【プロの音への第一歩】理詰めで学ぶミックス講座 第二回 – ミックスの流れ
作曲からミックスまでを一人で完結するのがスタンダードになって久しい昨今。DTM初心者~中級者にとっては、ミックスについて人それぞれ言うことが違って、何が正しいのか分からないという状況に陥りがちです。
そんな迷える人々を導いてくれる「理論」に沿って、ミックスについて解説していきます。
| 第一回 ≪ なぜ「ミックス」をするのか? |
第三回 ステレオイメージ編 ≫ |
初回から大好評の理詰めで学ぶミックス講座シリーズ第二弾。今回は、筆者のミックス手順をベースに、ミックスの流れについて紹介していきます。
最初に注意いただきたいのは、ミックスの手順やスタイルはジャンルやツールによって大きく変わってきます。これから紹介するのはあくまでも現在の私のフローであり正解ではないので、参考程度に読み進めてください。
前提
ミックスの流れを説明していく前に、二つの前提を共有させてください。
上流で解決できることなら、なるべくそうした方がよい
音楽制作を料理に例えて、作編曲がレシピ、音素材が食材、ミックスが調理、マスタリングが盛り付けだとしたら、どれが重要ですか?
その他が一流揃いでも、レシピが悪ければ「方向性の分からない料理」になってしまうかもしれませんし、素材が悪ければ「調味料で誤魔化した料理」になってしまうかもしれません。調理の腕が悪くとも、レシピ通りに作れば十分に美味しい料理が出来上がります。
「良いアレンジ」「良い演奏」「良い録音」が揃っていれば、ミックスやマスタリングは補正作業を必要とせず、最小限の処理で最良の結果が得られます。もし前の段階に遡って修正することができれば、より良い作品にすることができるでしょう。
また、レシピや材料を無視すると美味しい料理は出来ません。同じように、作編曲や音素材がもつ意図を無視してミックスすることは最悪の結果を招くことになるので、エフェクトを掛ける前に本当に処理が必要かどうかを考えるようにしましょう。
ミックスを料理で例えるのは私がオリジナルではなく、昔から用いられています。そのぐらい共通点が多いので、思考を簡略化するために使ってみてください。
音の問題点に気付ける人でないと、ミックスは難しい
これは出来る出来ないの話ではなく、ミックスが上手い人ほどこのアンテナの感度が高いということです。
良質な音楽を分析しながら聞いたり、とにかく沢山ミックスしてリファレンス楽曲とどのように違うのかを聞き比べたりしながら、感度を高めていきましょう。
ミックスを始める前に
「ミックスを始める時に、先ず何をしますか?」と聞かれたら、あなたはどう答えますか?
何かに取り組む際は、最初に目標を定めると思います。これと同じように、ミックス作業に取り掛かる前に、まずは完成形を想像してみましょう。
作業しながら完成像を固めていく方も多いと思いますが、そういった方も時間に余裕があるときに試してみてください。
この時、リスナーにはベースとギターの違いを聞き分けられなかったり、一度に沢山の音を聴き分けられない人も多いことを前提として覚えておきましょう。リスナーが一度に認識できるパート数は2~4つ程度と仮定して、セクション毎にどのトラックにスポットを当てるのかを考えておくと良いでしょう。
次に、楽曲を聴きながらそれぞれのトラックがどのような役割をしているのかを理解しておきましょう。
ポピュラー楽曲では大きく分けてリズム、コード、メロディー、その他FXに分類しておくことが多いです。ここで注意したいのが、役割は「楽器」によって判断するのではなく、「演奏」によって判断する必要があるということ。ギターやピアノはコードの役割を担うことが多いですが、カッティングギターをリズムに分類したり、単音主体のピアノをメロディーに分類することもあります。
ミックスの手順
それでは本題となる、ミックスの手順を見ていきましょう。
- トラックを並べる
- マスターバスにリミッターを適用
※一般的な手順ではありません。後述の詳細をご覧ください。
- ゲインとパンニングの調整
- 音声編集(ノイズ除去等)
- トラックエフェクト: 下ごしらえ
- トラックエフェクト: 音作り
- トラックエフェクト: 最終調整
- マスターエフェクト: 仕上がり調整
1. トラックを並べる
あまり多く語ることはありませんが、作業性に大きく影響するので意外と重要です。
この時、トラックの役割毎に並べるのがおすすめです。私の場合、リズム→コード→メロディとパートを乗せていくように作業を進めていくので、ミキサー画面のスクロールを最小限に抑えることができています。
更に具体的に言えば、[パーカッション]-[その他のドラムパーツ]-[ハイハット]-[スネア]-[キック]–[ベース]-[その他のリズムセクション]…と並べることで、低域を担うキックとベースの調整をやりやすくしつつ、打楽器とトーナルなリズムセクションを個別に調整しやすくしています。
このように、自分が作業する上でどの並びであればやり易いか、ミスに気が付きやすいか等、しっかり考えながらトラックの並べ方を確立していきましょう。
2. マスターバスにリミッターを適用
ミックスが完了していざリミッターを掛けてみたとき、「何かイメージと違う」といった経験はありませんか?
マスターバスにインサートされたエフェクトは、ミックス全体のイメージをガラリと変えてしまう程大きな効果があります。
であれば、予め「この程度の音圧が欲しい」というくらいにリミッターを設定してあげることで、仕上がりイメージを確認しながらミックス作業を進めることができます。
また、予め目標とする音圧が得られている状態であれば、普段大きめに音楽を聴いている時と同じようなボリュームで作業を進めることができます。ミックスをする時にどのくらいの音量で作業すればよいのか迷っている方にもおすすめです。
私の知る限りではあまりメジャーな手法ではないので、興味のある方は一度試してみてください。
尚、使用するリミッターはマルチバンドタイプではなくシンプルなシングルバンドタイプを選びましょう。マルチバンドタイプは周波数バランスを整える方向に働くため、「リミッターをバイパスしたらバランスが崩壊していた」ということになりかねません。
人間が何か作業する際は、入力-思考-出力という段階を踏みますが、その入力にあたる「モニターする音(耳に入る音)」は非常に重要です。このようにリミッターを予め掛ける方法は、完成形を意識しながら作業が進められる反面、元素材に対する配慮が疎かになってしまう可能性があるというメリデメの関係があります。
もしこの方法を試す際は、要所でリミッターをバイパスして素材が破綻していないか、各トラックが適切なバランスに保たれているかを確認しましょう。
尚、リミッターで設定する音圧に関しては適正な音圧とは?という記事をご参考いただき、曲想に相応しいと思われる設定を行ってください。
3. ゲインとパンニングの調整
各トラックへエフェクトを掛けていく前に、先ずは完成形になるべく近くなるようにゲインとパンニングを調整します(私はフェーダーではなく入力ゲインで調整する方が楽なので好みですが、フェーダーで整えても問題ありません)。
前回「周波数」の段でも触れた通り、なるべくトラックのソロモードを使わずにミックスを進めることが重要です。そのためには、ボリュームやパンが調整された状態でないと作業がし辛くなってしまいます。
ミックスの土台作りとなるので、ゲイン/パンニング両方を熟慮した上で設定していきましょう。特に、後からパンニングを変更するとなれば、エフェクトの調整をやり直す必要が出てくるなど手戻りになってしまう可能性があります。
4. 音声編集(ノイズ除去等)
必要に応じて素材の音声編集を実施します。ノイズ除去、ピッチ補正、ブレスの削除、タムの無音区間削除、入力遅延によるズレの調整などが挙げられます。
ここで重要なのは、必要性を見極めるということです。例えばタムの無音部分の除去はクリアなドラムサウンドを目指す場合には良いですが、滲み感が必要とされる曲想の場合は除去しない方がよい場合もあります。
判断が難しいところでは、ピッチ補正は演奏者の意図から外れてしまう可能性があるため、極力やりたくない処理です。しかし、他のトラックとミックスした時に歪みになる場合があるため、ミックスの結果と照らして後から調整することも念頭に置いておきましょう。
5. トラックエフェクト: 下ごしらえ
本題とも言えるエフェクト処理を施していきます。「とりあえず何か入れてみる」ではなく、エフェクトチェインの上部からそれぞれ意図をもって処理していくことが重要です。
エフェクトの最上段では、必要なトラックにだけ下ごしらえを施していきます。ここでの下ごしらえは素材の問題点を修正する「補正」の意味合いが強いので、基本的にデジタル系のプラグインを使用します。
音を変えることが目的ではなく、極力音を変えずに問題を解決することを目指します。具体的には不要な帯域のカット、極端にトランジェントが強い素材等ダイナミクスの調整、位相が乱れている素材の補正などが挙げられます。
また、ここではあいまいな人間の耳に頼るだけでなく、メーターをしっかり活用しましょう。コリレーション・メーターを用いれば位相の状態を簡単に確認することもできますし、周波数アナライザを見れば「よく聴こえないけれど超低域成分が含まれていた」ということも容易に発見できます。
よくある例としては、ギタートラックの不要な低域をローカットすることによって、ベースやキックの帯域を空けることができ、分離感・明瞭感を向上させることができます。逆に、素材をそのまま活かしたい時や滲み感が欲しいときはローカットしない方が良いケースもありますので、曲想に応じて判断していきましょう。
尚、エフェクトには必ず副作用(イコライザの位相変化やリンギング等)があり、良くも悪くも“素材を変えている”ことを肝に銘じておきましょう。
6. トラックエフェクト: 音作り
下ごしらえが済んだら、必要なトラックにだけ音を変える処理を施します。
ここではトラック単体で望む音色へと作り込んでいくだけでなく、他のトラックとの兼ね合いを見ながらダイナミクスや周波数のバランスを合わせたり、棲み分けさせたりしていきます。
音を変えるためには、アナログ系のプラグインを使用すると効果的です。
例えば、周波数がぶつかっている楽器があり、ステレオイメージやダイナミクス処理で棲み分けできない場合は、一方に音の重心を変えるような処理を施します。パルテックタイプのEQ、プリアンプやテープマシンを模したハーモニック/サチュレーション系プラグインなどが有効です。
コンプレッサーを掛けるにしても、パンチ感を求めて1176のようなFETタイプを選択するか、独特な抑揚を求めてLA-2Aのようなオプトタイプを選択するかといった、多くの選択肢があります。コンプレッサーについてはこちらの記事でも紹介していますが、使用するエフェクトの特性を把握して選択していくことが大切です。
また、曲想に合うようにサウンド・メイキングしたいトラックがあれば、ここで実施していきます。この段階で、全体が良く混ざっている状態まで追い込んでいきます。
エフェクト全般に言えることですが、エフェクトが有効な状態と無効な状態の聴感上(またはラウドネス値)の音量が揃うように、アウトプット・ボリュームを調整しましょう。
これによって、エフェクトをON/OFFして本当に望んだ効果が得られているのかを判断しやすくなったり、エフェクトの設定を変更した際に後段のエフェクトに対する影響を最小限に抑えることができます。
7. トラックエフェクト: 最終調整
最後に、全体がより良く混ざるように調整していきます。被りを抑えるイコライジングや、ステレオイメージの調整、トランジェントの調整を行います。
下ごしらえと同じような考え方で進めていきますが、先ほどは音声素材の問題に対処するための処理であったのに対し、ミックス全体を見据えた調整を行っていきます。全てのトラックで実施せず、2割ほどのトラックに施す程度に留めます(それ以上調整が必要な場合は、手順をさかのぼって根本を解決しましょう)。
尚、被りを抑えるイコライジングを施す場合は、重要度の高いトラックはそのままに、重要度の低いトラックに対して実施します。このように、誰が主人公で誰がよけるのかをしっかり意識しながら調整していきましょう。
8. マスターエフェクト: 仕上がり調整
最後に、マスターバスにエフェクトを挿してミックス全体を調整します。
ここで意識するのは「求める曲想に沿った音色・音像への調整」と「リスニング環境を想定したバランス調整」の2軸です。本来はこれまでの作業で完璧に仕上げるのが理想ですが、ミックス全体の周波数バランスを整えたり、ダイナミクスの差が激しい場合は均すようなコンプレッサー処理を掛けていきます。
また、色調を整える方向性では『GULLFOSS』のようにサウンドを鮮明にするエフェクトを活用したり、テープシミュレーター等で暖かみやくすみを入れていくといった調整を施していきます。
最後にリミッターの設定を微調整したり、より良い効果が得られるのであればマルチバンドタイプに置き替えたりして完成です。
さいごに
第二回となる本稿、いかがでしたでしょうか?
第一回で触れた「音の三要素」について具体例をご紹介する予定でしたが、エフェクト・チェインの順序と考え方も非常に重要なファクターであるため、先にご紹介しました。
ちなみに私は、リミッターにハードクリッパーを使用しています。通常のリミッターと比較してトランジェントが失われないことに加え、下手なミックスをするとすぐに歪みとなって現れるので、非常に良いトレーニングになります。
このように、私のスタイルは王道とは異なるもので、ご紹介した流れが皆様にとって正解とは限りません。
皆様も日々のミックス作業においてなぜこのトラックから着手したのか、なぜこのエフェクトをインサートしたのか、頭で描いた音のイメージを実現できているかなど、一挙手一投足について疑問を投げかけ、自分のスタイル(理論)を築いていってください。
第三回以降では、サウンドも交えて解説していく予定です。お楽しみに!
| 第一回 ≪ なぜ「ミックス」をするのか? |
第三回 準備中 ≫ |
■関連記事
folder NEWS, SONICWIREニュース, クリプトンDTMニュース, プラグイン・エフェクト, 活用方法
label tips, エフェクト, セミナー, ミックス, 理詰めで学ぶミックス講座