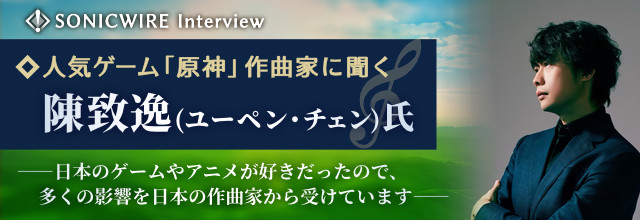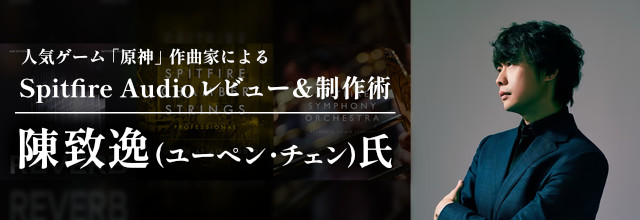
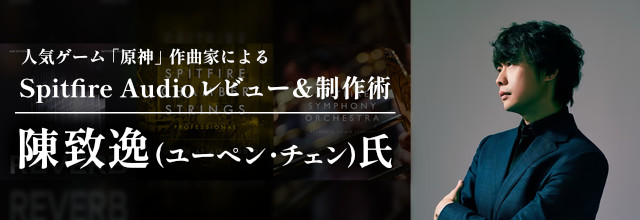
人気ゲーム「原神」作曲家が明かす、独自の楽曲制作術とSpitfire Audio製品の魅力
世界的な人気を誇るオープンワールドRPG「原神」をはじめ、数々の作品で壮大かつ美麗なオーケストラサウンドを生み出してきた作曲家、陳致逸 (ユーペン・チェン) 氏。
本インタビューは2回に分けてお届けします。第二回の本記事では具体的な制作ワークフローや、Spitfire Audio製品のレビュー、そして未来の音源への展望まで、その制作の深層に迫ります。
(第一回では音楽的ルーツや「原神」の音楽制作秘話について伺いました。第一回はこちら↓)
楽曲制作のプロセス ――「演奏」から生まれる音楽
作曲する際、メロディー、リズム、ハーモニーはどのような順序で構築していくのですか?
私の創作では、まずメロディーから書き始めます。その際、簡単なハーモニーも同時に付けますが、メロディーが完全に固まってから、ハーモニーをより精緻に磨き上げていきます。リズムの調整は最後です。リズムのデザインや配置は比較的自由度が高く、いつでも変更できるからです。
優れたメロディーは、リズムやハーモニーの設計を少し変えるだけで、喜怒哀楽といった豊かな感情を表現し、さまざまなシーンに対応できます。私は、メロディーこそが最も重要だと考えています。
1曲あたりの制作時間はどのくらいですか?
曲によって様々ですね。インスピレーションが湧いた時は、ピアノと弦楽器、あるいは独奏楽器とシンプルな伴奏といった構成で、15分以内に完成させることもあります。
一方で、複雑な戦闘曲の場合は、1~2週間、時にはそれ以上かけて繰り返し推敲します。伴奏の設計、ハーモニー、メロディーの変奏、セクションの構成、そして各楽器が登場するタイミングや組み合わせまで、全てが合理的かつ完璧になるように練り上げます。1曲に丸々1ヶ月を費やすことも珍しくありません。
普段の制作環境についてお伺いします。DAWは何をお使いですか?
DAWは『Cubase』を使っています。
まず、Cubaseのようなシーケンサーソフトの中で、作曲と編曲を同時に進めます。これで、まずは聴ける状態のMIDIデモが完成します。
このデモを監督やゲームプロデューサーに確認してもらい、OKが出たら、私のアシスタントが楽譜作成ソフト「Dorico」を使ってスコアを制作します。そして、出来上がった楽譜を見ながら、私はもう一度、作曲・編曲の修正を行います。
私の創作は、編曲(MIDIデモ制作)と楽譜化の2つのステップに分かれていて、両方の段階で修正を加えます。そして最終的に、本物のオーケストラを呼んでレコーディングを行う、という流れです。
前回の記事ではクラリネットのご経験があると伺いましたが、それが現在の制作スタイルに活かされている部分はありますか?
もちろんです。私はクラリネットを吹いていたので、このスキルを制作にも活用しています。管楽器や、時には弦楽器のパートも、自分で作ったブレスコントローラー(MIDIのデータを息で入力できる機器)を吹いて入力しているんですよ。実際に「演奏」しながら編曲することで、より人間らしい息遣いを表現できるのです。
『Spitfire Symphony Orchestra』――「聴いた瞬間、AIR Studiosの記憶が蘇った」
それでは、今回試していただいた製品について伺います。まず『Spitfire Symphony Orchestra』の第一印象はいかがでしたか?
非常に素晴らしいですね。実は私「原神」のモンド地域の楽曲を、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と共にロンドンのAIR Studiosでレコーディングした経験があるんです。ですから、あのスタジオの響きは私の記憶に深く刻まれています。
この音源を鳴らした瞬間、まさにAIR Studiosのサウンドそのものだと分かり、当時の記憶が鮮明に蘇ってきました。あのレコーディングスタジオのサウンドが、私は本当に好きなんです。
音色や操作性について、特に気に入った点を教えてください。
最大の魅力は、最初からAIR Studiosの響きが含まれている点にあります。他の音源を使うときは自分でリバーブを加えたり、様々な設定を追い込む必要がありますが、この音源は全てのパートに統一感があり、後処理の手間が大幅に省けます。聴いた瞬間に「これが正しいオーケストラの音だ」とわかる。これは作曲家にとって非常に大きなアドバンテージです。
特に気に入っているのはEnsemble(アンサンブル)パッチです。インスピレーションが湧いた時に、鍵盤で全体のハーモニーをすぐ確認できるので、楽曲の骨組みを素早く作るのに非常に便利ですね。
操作性も合理的でシンプルです。私はブレスコントローラーを含め複数のMIDIコントローラーを使ってキースイッチの切り替え等を行っていますが、この音源はわずか3つほどのMIDI CCで多彩な表現を自在にコントロールできるよう、非常に効率的に設計されています。
表現の幅を広げる『Spitfire Chamber Strings』 & 『AIR Studios Reverb』
『Spitfire Chamber Strings』はどのような印象でしたか?
『Spitfire Symphony Orchestra』に比べてサウンドは派手ではありませんが、よりクリーンで繊細ですね。J-POPなどのポピュラー音楽に非常に適していると感じました。
『Spitfire Symphony Orchestra』の重厚なサウンドでは表現しきれない、より繊細で細やかな表現が必要な時に、この音源がその隙間を完璧に埋めてくれます。作品の目的に応じて、『Spitfire Symphony Orchestra』と使い分けることで、表現の幅が大きく広がるでしょう。
『AIR Studios Reverb』はいかがでしたか?
これも素晴らしいです。まさにAIR Studiosの響きそのものを再現できます。試しに、私が普段使っているVSLの音源にこのリバーブをかけてみたところ、サウンドが完全にAIR Studiosの雰囲気になりました。今では、異なるデベロッパー製音源の質感を統一する手段として積極的に活用しています。
このリバーブは、センドではなく各トラックに直接インサートして使うのが気に入っています。その方が、よりAIR Studiosらしい音場感が得られますね。多くのパラメータを調整する必要がなく、インサートするだけですぐに最高のサウンドが得られる手軽さも魅力です。
ソフトウェア音源と生演奏、その本質的な違いと可能性
ソフトウェア音源と生演奏の最も大きな違いは何だとお考えでしょうか?
生演奏には、演奏家の本物の感情が込められます。そして、複数の楽器が同時に鳴った時、音の倍音が溶け合い、途切れることのない一体感が生まれる。それはまるで、音楽全体が呼吸しているかのようです。この“音楽の呼吸”こそが、聴き手の心を動かすかどうかを決定づける最大の要因だと考えています。
もちろん、ソフトウェア音源が決して悪いわけではありません。私自身、キャリアの初期には様々なソフトウェア音源を使いながら、オーケストレーションを学んできました。ソフトウェア音源は、作曲を学ぶ上で非常に優れたツールです。
ソフトウェア音源の音をそのまま最終的な楽曲に使うことはありますか?
あります。ソフトウェア音源の方が自分のイメージに近い場合、生演奏とソフトウェア音源を混ぜて使うことがあります。
特にピアノに関しては、レコーディングせずにソフトウェア音源で完結させることが多いですね。
ピアノだけソフトウェア音源を使うことが多いのはなぜですか?
ピアノの録音は非常に複雑なんです。ピアノ自体が高価ですし、求める音色によって違うピアノが必要です。例えば、ある曲のためにYAMAHAのピアノを買って、録音が終わったらそれを売って、今度はSteinwayのピアノに買い替える、ということも実際にやりました。私のスタジオはスペースが限られているので、非常に手間がかかります。
また、レコーディングした音が、必ずしも求めている音色になるとは限りません。そういった点で、ソフトウェア音源の方が手軽で、かつ効果的な結果を得やすいのです。
なるほど……普段よくお使いになるソフト音源はありますか?
ピアノ音源はSynthogyの『Ivory II』をよく使います。
あとはSpitfire Audioの打楽器の音源は非常にクオリティが高く、レコーディングの必要がないとまで思いますね。
オーケストラ音源は、以前はVSL (Vienna Symphonic Library)を最もよく使っていました。VSLの製品は全て購入したほどです。ただ、最近はSpitfire Audioの音源の方が、VSLに比べて操作がより手軽で便利だと感じています。最近作った2曲は、Spitfire Audioの音源を使って制作しました。
打ち込みの楽曲に生命感を与えるためのテクニックはありますか?
私はMIDIデータを非常に細かく作り込みます。特に、CC 1(Dynamic)だけでなく、CC 11(Expression)やCC 7(Volume)も併用し、オートメーションを丹念に書き込みます。この音量の変化こそが、サウンドに人間らしい生命感を与える最も重要な要素です。
また、複雑な表現をしたい場合は、単一の奏法(アーティキュレーション)に頼らず、複数の奏法の音源を組み合わせて一つの表現を作り上げています。
理想のバーチャル・インストゥルメント、そしてその未来像
「理想のバーチャルインストゥルメント」とはどのようなものだと思いますか?
私が理想とするのは、サンプリングではなく、モデリング技術に基づいた楽器です。プログラムによってサウンドをリアルタイムに生成するもので、VOCALOIDやSynthesizer Vの「楽器版」のようなものですね。
現在のサンプリング音源は、録音された音を再生するだけなので、時にその音源のスタイルに私の創作が影響されてしまう側面もあります。モデリング音源であれば、どのような音楽スタイルにも柔軟に対応できるはずです。サンプリング音源とモデリング音源を組み合わせて使うのが、今後の方向性ではないかと考えています。
本日は貴重なお話をありがとうございました!
folder NEWS, SONICWIREニュース, SPITFIRE AUDIO, インタビュー/レビュー, 活用方法
label SPITFIRE AUDIO