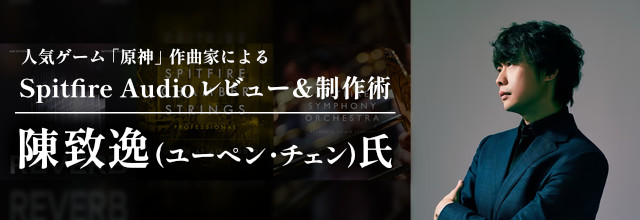音楽家・生形三郎氏が紐解く『BBC Radiophonic Workshop』――ミュジーク・コンクレートの世界
1958年、「BBC Radiophonic Workshop」はラジオやテレビで使用する効果音や革新的な音楽を制作するため、イギリスの公共放送局BBCによって設立されました。「ミュジーク・コンクレート」からの影響も受けつつ、当時最先端のテープ編集や音響合成を駆使したそのサウンドは、電子音楽やサウンドデザインの歴史に多大な影響を与えました。
そんな歴史的サウンドを、現代のクリエイターが体験できるよう再現したのがSpitfire Audioの『BBC Radiophonic Workshop』です。
今回は本作の魅力を深掘りするべく、録音技術やミュジーク・コンクレートに詳しい音楽家、生形三郎氏にお話を伺いました。
生形氏とミュジーク・コンクレート
はじめに、生形さんのご経歴と現在の活動についてお聞かせください。
音楽大学で作曲を学んでいた際に出会った電子音響音楽、いわゆる「ミュジーク・コンクレート」に衝撃を受け、アコースティックな作曲から一転してその世界に傾倒するようになりました。より深く学ぶため、大学4年次にはミュジーク・コンクレート発祥の地であるフランスにも渡りました。
卒業後も創作や演奏活動を続けながら、東京藝術大学大学院で研究を重ねました。修了後、現在は創作活動のほか、録音エンジニアリングや音響機器の評論へも活動の場を広げ、洗足学園音楽大学では准教授として教育にも取り組んでいます。
普段はどのような音楽を制作されているのでしょうか?
ミュジーク・コンクレート的な楽曲や、その要素を取り入れつつ環境音やアコースティック・ピアノの演奏を織り交ぜた音楽を制作しています。また、主にクラシック音楽の録音エンジニアとして演奏家の作品作りをサポートするかたわら、フィールドレコーディングもライフワークとしています。
今回のテーマでもある「ミュジーク・コンクレート」とは、どのような音楽なのでしょうか?
ミュジーク・コンクレートは1940年代初頭、新たな音楽語法を開拓するため、音の響きだけを用いて音階や機能和声などに代わる音楽言語を見出そうと始まった音楽です。
例えば、ドアの開閉音や列車の走行音、食器やおもちゃを叩いた音など、あらゆる録音素材を編集して作曲することで、メロディやハーモニーで表現する音楽とは全く異なるアプローチで、自在に音楽を表現します。
生形さんのミュジーク・コンクレート作品
生形さんが考える、ミュジーク・コンクレートの魅力とは何でしょう?
音のイメージを音符に置き換えて作曲する通常の音楽と異なり、頭の中にある音楽や音のイメージを思い浮かんだまま自由に形にできる点に最大の魅力を感じます。楽譜を介さず、完成後の音響をリアルタイムに聴きながら制作・コントロールできることにも惹かれますね。
録音とサンプリングの世界
ここからは録音全般について伺います。フィールドレコーディングの経験で、特に印象深いものはありますか?
フィールドレコーディングの経験は、時間が経っても強く印象に残っているものが多いです。例えば、新潟県小千谷市片貝町で江戸時代から続く、片貝まつりの4尺玉花火。その怒涛の超低音は他では決して得られません。ナレーションとともに行われる奉納花火自体の様子や、四尺太鼓の演奏、山車を引き回す掛け声など、お祭り全体の雰囲気は絶対に忘れられない経験です。
また、島に渡って録音した波や自然の音も、車の音など人工音が一切含まれないため、それだけで非日常的で印象深いサウンドになります。
環境音を音楽素材として使う場合と、効果音として使う場合で、録音時のアプローチに違いはありますか?
映画などで使う場合は、シーンを説明するための「サイン」となる音を明確に録音する必要があります。そのため、音の種類や距離、響きといった「情報」が音に含まれていることが重要になります。
一方、音楽で使う場合は、音楽の一要素として、周波数的なバランスやレベルがどうなのか、また、その音を聴いた人がどんなイメージや記憶を想起するかに意識を向けて録音することが重要になってくると思います。
サウンドを録音する際のこだわりや、心がけていることがあれば教えてください。
音楽でも環境音でも、録音はある意味で一期一会です。タイミングを逃さないよう万全の準備を整えること、そして、録音する以前に、音そのものを「よく聴く」ことが何より大切だと考えています。
普段使用されている録音機材で、特に気に入っているものはありますか?
フィールドレコーディングでは、コルグのDSDレコーダーで録る音が生々しくて気に入っています。
ヴィンテージ機材の存在感ある音も好きですね。外部スタジオではスタジオの定番機材を使うことも多いですが、自宅ではNAGRAのオープンリールデッキやSTUDERのミキサーを使ってグランドピアノをよくレコーディングします。
楽器の録音と効果音の録音では、使用機材も大きく変わるのでしょうか?
歌や楽器の録音には、新旧の定評あるスタジオ機器を用いることが多いです。逆にフィールドレコーディングでは、天候などシビアなコンディションでの録音も多く、ハンドリングの良さや機能性を重視するため、新しい機材を使うことがほとんどです。
技術の発展とともに手法は変化しましたが、サンプリングの概念は現代にも受け継がれています。生形さんが感じる「サンプリング」の魅力とは何でしょうか?
サンプリング、つまり録音することで、音をその発生原因から切り離せるようになり、聴き手や作り手にとって新たな意味やイメージが生まれる。それが最大の魅力だと思います。そして、加工や編集を経ることで、今まで聴いたことのない斬新な聴覚体験が実現します。
『BBC Radiophonic Workshop』レビュー
まず、実際に『BBC Radiophonic Workshop』に触れてみた第一印象はいかがでしたか?
歴史的なサウンドのアーカイブというだけあって、実験的でありながらも、どこか懐かしさを感じる「音の玉手箱」のような製品ですね。
現代の機材では再現しきれない、この製品ならではの質感や個性はありましたか?
やはり、ヴィンテージなシンセサイザーや録音素材が生み出す独特の存在感は大きな魅力です。その音一つで、場の雰囲気を強烈に染め上げるような強いインパクトを持つものがたくさんあります。
特に気に入ったサウンドや、印象的だったパッチを教えてください。
パッド系の音色では、「Meditation Organ」の深く荘厳なサウンドに魅了されました。「Macra Brighton」や「Metropolitan Dawn」といった重層的な音もいいですね。
ヴィブラフォンも印象的で、「Fresh Vibes」や「Vibraphonic Glow」などは様々な音楽に幅広く使えそうです。
また、リズムキットとして使える「Junk Percussion」や「Maida Vale Sounds」も、一味違うグルーヴをトラックにもたらしてくれるのではないでしょうか。
それから、「Cloning Miniaturisation」や「Pensive Arctic Stomp」、「Sutekh Time Tunnel」、「5 Big Booms」などは大変強烈な雰囲気を備えており、一音加えるだけで独特の世界観へと引き込んでくれます。
生形さんご自身は、BBC Radiophonic Workshopのどのような点に歴史的な価値や魅力を感じますか?
電子音響制作の黎明期に、意欲的に音の実験や冒険を重ねて独特のサウンドを作り上げたことは、歴史的にも大変意義深いことだと思います。また、同時期に世界各国で創設された同様の機関に比べ、ラジオやテレビ番組の特殊効果音の制作に主眼を置いていたこともあり、実験的ながらもどこかユーモアを感じる、親しみやすいサウンドメイクが素敵ですね。
本作のように歴史的な音をアーカイブすることの価値について伺います。もし日本のサウンドをアーカイブするなら、どのようなものが面白いと思われますか?
すぐに思い浮かぶのは、ゴジラなど特撮もののサウンドですね。作曲家の伊福部昭は、手袋でコントラバスの弦を擦ってゴジラの鳴き声を生み出しましたが、ウルトラマンなどを含め、日本の歴史的な特撮ものの個性あふれるサウンドはアーカイブに値する魅力が詰まっていると思います。また、松本零士作品のシリーズや、ガンダムに代表されるスーパーロボット系アニメの数々の効果音も大変面白いのではないでしょうか。
また、作曲家の武満徹はミュジーク・コンクレートの技法を取り入れた映画音楽も手掛けています。そうした特徴的で歴史的にも意義深い、黎明期の映画音楽のサウンドをアーカイブすることも興味深いですね。
本作はサウンドデザインのツールとしても強力ですが、どのような作品で活かせそうだと感じましたか?
とりわけ、映画や舞台、ゲームなどの劇伴音楽や音響制作で、非日常的な空気感や世界観が欲しい時に非常に有用な音源だと思います。音の傾向はダークでエクスペリメンタルなものも多いですが、あえて綺麗めなサウンドの裏に忍ばせることで、主役を一層引き立てるスパイスとしても、もってこいではないでしょうか。私自身も、さっそく自身の音楽作品で取り入れてみたいと感じています。
ずばり、本作はどのような人におすすめしたいですか?
映画やゲームなど、劇伴系のクリエイターの方々にとっては即戦力になる製品と言えるでしょう。また、純粋な音楽作品を作る方にとっても、メインの要素としてはもちろん、隠し味として使うことで、音楽に広がりや深みを与えてくれる魅力的なライブラリーだと思います。
本日は貴重なお話をありがとうございました!
(音楽家/録音エンジニア/オーディオ評論家)
音楽大学で作編曲、特にミュジーク・コンクレート(電子音響音楽)を学び、フランスへ留学。現在は創作活動の傍ら、洗足学園音楽大学で准教授として後進の指導にあたる。
作曲、録音エンジニアリング、フィールドレコーディング、オーディオ評論、執筆活動など、「音楽」と「オーディオ(録音・再生)」の両面から多角的にアプローチ。「音」の持つ魅力を広く伝える活動を行う。
主な著書に『クラシック演奏家のためのデジタル録音入門』(音楽之友社)、月刊『ステレオ』誌での連載など。レコーディングエンジニアとしても、クラシック音楽を中心に多くの作品を手掛け、高い評価を得ている。
folder NEWS, SONICWIREニュース, SPITFIRE AUDIO, インタビュー/レビュー, クリプトンDTMニュース, 活用方法