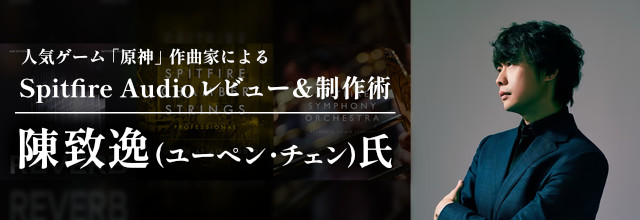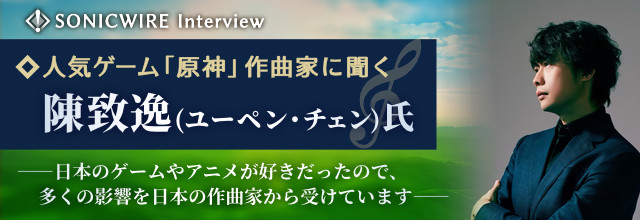
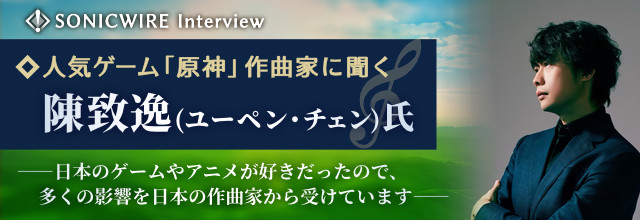
人気ゲーム「原神」の音楽の舞台裏―作曲家:陳致逸 (ユーペン・チェン) 氏インタビュー
世界的な人気を誇るオープンワールドRPG「原神」をはじめ、数々の作品で壮大かつ美麗な音楽を生み出してきた作曲家、陳致逸 (ユーペン・チェン) 氏。彼の音楽は、なぜこれほどまでに多くのリスナーの心を惹きつけるのでしょうか。
本インタビューは2回に分けてお届けします。第一回の今回は、陳氏の音楽的ルーツや、「原神」の音楽制作秘話に迫ります。
(第二回では製作のワークフローやSpitfire Audio製品のレビューをご紹介しています。第二回はこちら↓)
音楽ルーツと日本のゲーム・アニメ音楽からの影響
本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。はじめに、ご自身の音楽的なバックグラウンドについてお聞かせください。
まず、私の音楽センスは母譲りのものだと思っています。母は声楽家で、私が生まれる前は常にステージで歌っていました。私を妊娠してからはそのキャリアを諦めましたが、お腹の中にいた時から毎日母の歌を聴いていたので、きっと自然とメロディーに対して非常に敏感になったのでしょう。父は数学の教師ですが、両親ともに私が音楽の道に進むことをとても応援してくれました。
中学校に上がるころには、私は音楽の道に進むことを決めていました。芸術系の学校に進み、高校を卒業するまでの6年間、クラリネットを専攻しました。そして大学に入る際に作曲へと専攻を変えたのです。
クラリネットから作曲へと転向されたきっかけは何だったのでしょうか?
当時クラリネットは熱心に練習していたため、短期間で演奏技術のほとんどを習得してしまいました。そして、学校の吹奏楽団や合唱団に参加して自分のパート以外の様々な楽器の音や総譜(スコア)に触れるうちに、作曲そのものへの興味がどんどん大きくなっていったのです。
その過程で多くのクラシック音楽に触れ、100年、200年前に生きていた作曲家が書き残した音符を、現代の我々が演奏することで、まるで彼らの魂が蘇るような感動的な体験をしました。音楽が人々に与える影響力に感銘を受け、自分も作曲家になろうと決意したのです。
陳氏の音楽からは日本のコンテンツからの影響も感じられますが、特に印象に残っている作曲家や作品はありますか?
この話題は長く語れますよ(笑)。子供のころから日本のゲームやアニメが好きだったので、私の音楽は日本の作曲家たちから本当に多くの影響を受けています。
ゲームでは、すぎやまこういち先生の「ドラゴンクエスト」。彼の音楽がきっかけで、彼が音楽を担当した多くのゲーム作品をプレイしました。そして「ファイナルファンタジー」の植松伸夫先生。アニメでは宮崎駿監督の作品が好きでしたね。久石譲先生や坂本龍一先生の音楽もよく聞いていました。彼らの楽曲は今でも私のプレイリストに入っていて、よく聴き返しています。
また、幸運なことに、大学時代には谷村新司先生の講義に参加する機会もあり、彼の楽曲からも多くのインスピレーションを受けました。
「原神」の音楽制作 ―― 信頼が生んだ自由な創作環境
どのような経緯で「原神」の音楽制作に参加されたのでしょうか?
長年の友人であるCai Zoe氏に誘われてmiHoYoに参加しました。「原神」の開発初期から関わっていたので、このゲームについては深く理解できました。音楽制作は最初から順調に進んだわけではなく、多くの試行錯誤を重ねて方向性を探っていきました。
その過程で幸運だったのは、ゲームプロデューサーである蔡浩宇氏の信頼とサポートを得られたことです。彼は私に様々なアイデアや可能性を試す機会をくれ、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、上海交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団といった世界トップクラスの楽団とのコラボレーションにも挑戦することができました。これらの貴重な経験は、私の視野を大きく広げてくれましたね。
「原神」では、主にどの地域の音楽を担当されましたか?
miHoYo在籍中は、主にモンド、璃月、稲妻、そしてスメールの一部の音楽を担当しました。その他、ログイン画面の楽曲や一部のキャラクター紹介PVの音楽なども制作しています。
ログイン画面の楽曲には心を揺さぶられ、作品の世界に引き込まれました。心に残るメロディーはどのように生み出されるのですか?
ある種のメロディーは、論理では説明しきれないほど、まさに突然湧き上がるように生まれることがあります。まるでメロディー自体が「降臨」してくるような感覚ですが、そうして生まれたものこそが最も人の心を打ち、非常に貴重なものになります。
人々の心に触れ、共感を呼び、そして長く記憶に残るメロディーや音楽を書き続けること。それが作曲家としての最大の使命だと考えています。
身近な出来事からインスピレーションを受けた楽曲はありますか?
はい、あります! 私の家族はよくインスピレーションの源になります。例えば、「原神」のキャラクター「クレー」の音楽は、私の娘から着想を得ました。私にとって作曲とは、人生や日々の出来事を記録し、その貴重な感情を旋律に変換する作業でもあるのです。
また、「シロガネヨシの如く(Lover’s Oath)」という曲は、まさにインスピレーションが爆発した産物で、一瞬のうちにメロディーが頭の中に現れました。ゲームのカットシーンで一度しか使われていないにもかかわらず、今でも多くの音楽プラットフォームで再生されていると聞き、とても驚いています。この曲を愛してくださる皆さんに感謝しています。
各地域の文化を音楽に昇華させるアプローチ
モンド、璃月、稲妻など、各地域の音楽を創る上で、どのような準備や調査をされましたか?
本格的な作曲に入る前に、まずその地域の文化に関連する伝統音楽の資料を研究し、楽器の構造を深く理解します。そして、それらの楽器の演奏を大量に聴き、その独特な表現を体感するのです。
例えば「稲妻」の音楽を作る際は、日本の伝統音楽家や現代作曲家の作品を数多く聴き、三味線や尺八といった民族楽器とオーケストラをどのように融合させるかを学びました。「璃月」の時も同様に、中国の民族楽器や古典的な民謡を研究しました。その上で、メロディーの中から最も記憶に残る要素を抽出し、自身の音楽的感性と融合させて楽曲に落とし込んでいきます。
特に「稲妻」の音楽では、和楽器とオーケストラの融合が非常に自然でした。制作で難しかった点はありますか?
多くの困難に直面しましたが、最大の問題は日本の伝統楽器のチューニングが西洋のオーケストラ楽器とは異なる点でした。これは中国や他の地域の民族楽器でも同様の問題で、それこそが楽器のユニークな音色の源なのですが、オーケストラと合わせる際には解決しなければなりません。
基本的なアプローチとしては、伝統楽器の演奏家にできるだけオーケストラの調律に近づけてもらい、レコーディング時には各楽器を個別のトラックに録音します。そうすることで、後のミックスダウン作業で調律のズレを調整する余地が生まれるのです。
「原神」音楽の核心と、これから
「原神」の音楽が持つ独特の世界観は、どのような創作理念から生まれているのでしょうか?
「原神」の音楽では、各シーンのBGMの主題と、キャラクターのテーマ曲の主題が相互に呼応するように作られています。また、戦闘音楽には一貫したモチーフがあり、地域が変わるとそのテーマが変奏されます。このような主題の発展や変奏といった手法は、私がずっと大切にしてきた創作理念です。
「原神」の音楽の独自性は、その物語性にあると考えています。単にBGMとしての機能を満たすだけでなく、音楽がゲームのストーリーを語り、時には言葉以上の意味を表現する役割を担うことで、プレイヤーの心に深い記憶を刻むのです。
「原神」での経験は、現在の音楽スタイルにどのような影響を与えましたか?
「原神」の音楽制作を通じて、私の創作理念は進化し、自分自身の音楽言語を見つけることができました。そして、世界中のより多くのリスナーに私の作品を聴いてもらえたことは、大きな自信に繋がっています。
もちろん、この成長は「原神」だけからもたらされたものではありません。現在制作しているゲーム「逆水寒 (Sword of Justice)」でも同様の感覚を抱いています。作曲家にとって、このように常に前進し続ける状態は非常に重要です。
今後の活動や目標、夢についてお聞かせください。
現在はmiHoYoを離れ、ドイツのグラモフォンと協力してレコードを複数制作しています。自分の音楽スタイルをさらに広げ、新しいことに挑戦していきたいと思っています。将来的にはコンサートなど、表舞台に立って演奏する機会も持ちたいですね。
また、自分の作品をより良く、優れたものにすることで自身の創作能力の限界に挑戦し続けたいとも思っています。良い作曲家になり、私の音楽を一人でも多くの人に聞いてもらうことが私の夢です。今後もゲームや映画といった分野で、得意とするオーケストラ音楽を軸に、様々な音楽スタイルを融合させながら創作を続けていきたいと思っています。
最後に、日本の若手作曲家へメッセージをお願いします。
日本のクリエイターの皆さんの、その専門性と努力する精神は、私が常に学ばせていただいているところです。なので「一緒に頑張りましょう」と伝えたいですね。
作曲家への道は決して平坦ではありません。私も「原神」で多くの方に知っていただけるまでには、広告音楽から映画、ドラマまで、様々なプロジェクトを経験し、非常に長い下積みの時間がありました。その努力の積み重ねがあったからこそ、今の結果がついてきたのだと思います。だから、ご自身の夢を、どうか信じて持ち続けてください。そして、決して諦めないでください。
そして、他の作曲家の作品を参考にすることを恐れないでください。私も常に他の素晴らしい作品から、良いと思った要素を自分なりの解釈で取り入れています。たくさんの経験を積み、学んでいく過程で自分自身のスタイルが見つかっていくものです。学ぶことをやめてはなりません。
本日は貴重なお話、ありがとうございました!
folder NEWS, SONICWIREニュース, インタビュー/レビュー
label